星野智幸
1965年アメリカ・ロサンゼルス生まれ。1997年『最後の吐息』で文藝賞、2000年『目覚めよと人魚は歌う』で三島由紀夫賞、2003年『ファンタジスタ』で野間文芸新人賞、2011年『俺俺』で大江健三郎賞、2015年『夜は終わらない』で読売文学賞、2018年『焔』で谷崎潤一郎賞を受賞。新聞連載していた『ひとでなし』を、2023年夏に刊行予定。

 Illustration 塩川 いづみ
Illustration 塩川 いづみ
コロナ禍が始まってしばらくしたころ、風の便りが電子メールで届いて、kaze no tanbunを書きませんか、と誘惑された。
「『短文 tanbun』にかんしては、さまざまな解釈ができるかと思いますが、小説やエッセイでもいいですし、同時に小説やエッセイでなくともかまいません。」と説明してある。というか、説明を放り投げている。
そして最後を、「どうか、版元のことも編集者のことも読者のことも念頭からぬぐって、ただご自身の望むようにご執筆ください。それがわたしたち三人の希望です。」と結んである。
読む人の存在をいっさい消し去って書いてよい、と?
こんな魔の誘惑に落ちない人間がいるだろうか?
私はたわいもなく落ちた。喜び勇んで魔の手に身をさしだした。
そうして柏書房から刊行されたのが、いろいろな書き手による短文アンソロジー、「kaze no tanbun」シリーズである。全3巻で、1巻目のタイトルが『特別ではない一日』、2巻目が『移動図書館の子供たち』、3巻目が『夕暮れの草の冠』。
ところで、誘惑してきた「わたしたち三人」とは誰か?
この「kaze no tanbun」シリーズを思いつき、編者となり、ご自身もtanbunを書いた、小説家で歌人で翻訳家でミュージシャンの西崎憲さん。この企画を推進した柏書房の編集者(当時)の竹田純さん。そして、この3冊のブックデザインを手がけた奧定泰之さん。しかし歌人、俳人、詩人とはいうけれど、小説人といわないのはなぜだろう。

シリーズ感のまったくない、てんでばらばらな装丁を見てほしい。本の判型も違えば、表紙の材質も異なり、色の統一感もゼロ、3冊を本棚に並べてもちぐはぐすぎて収まりが悪い。でも一冊一冊を手に取れば、その個性、自分はこうだという表現力の豊かさにうっとりする。一般のシリーズ本が制服のかっこいい私立の高校生だとしたら、kaze no tanbunはフリースクールの生徒だ。本当は4冊シリーズなのに1冊は今日は学校に来ていない、なんてこともありうるかもしれない。

書き手のラインナップも面白い。専門とする文章はそれぞれ違っていて、著名な人も、ほとんど名の知れていない人も、これが紙の本ではデビューとなる人も、ばらばらのまま集まっている。
どれを読んでもめっぽう心地よい。読んだことのある書き手の作品でも、作者名が溶けてしまう中で読むと、何か無名性の親しみが迫ってくる。知らない書き手のものも、同じ親しさが湧いてくるのが不思議だ。そして、こう書いたそばから裏切るけど、飛浩隆さんの作品は別格にすごい!
私が知らない方も少なからずいるので、最初はネットで検索してみたりしたが、すぐにやめた。「tanbun」の世界では、それを書いた人が何者かなんて情報は意味がないのだ。何なら、書いた人の名前を忘れたっていい。そこに並んでいる「tanbun」を好きなときに好きな順で読んで、好きなものだけ読んで、読んでいる現在に酔えばいい。読み終わってすぐに忘れてもいいし、何度も反芻(はんすう)してもいい。はずみがついて自分も書いてみたりしたっていい。暴力さえ振るわなければ、tanbunの世界に決まりは何もない。何をしてもいいのだ。
この自由。この解放感。この緩やかさ。言葉で言うのはたやすいが、現実の本として作り出すことは、じつは至難の業。
どうしてこんなことができるのだろう。

西崎さんのtanbunを読むと、それはうっすらとわかる。西崎さんの小説は、怪奇小説だったりファンタジーノベルだったり青春小説だったりSFだったり、ジャンルが強く意識されているものが多いと思う。さらには、「フラワーしげる」という名前で短歌も作る。言葉が作品となっていくための外枠、型について、西崎さんは知り抜いている。
にもかかわらず、私には西崎さんの文章は、どのジャンルにも収まらないと感じる。というか、西崎さんの文を読んでいると、ジャンル分けに本質的な定義も意味もないんだな、と思うほかない。どれほどお洒落しようが、おざなりの身なりでいようが、制服を着ようが、コスプレしようが、女装しようが男装しようが、服を着るという行為はすべて仮装であると知っている、というか。そんな仮装をこよなく愛していて本気で楽しんでいる、というか。それは各巻が好き勝手な装いをしている装丁にも、濃密に表されている。
でも大半の現代の人間は、服を着ないで生活することは難しい。仮装ではあっても、服を着ることは日常であり、生きることの基盤になっている。
だから言葉と似ている。言葉なしで人間は生きることは難しい。でも、言葉にはいろいろな種類があって、日本語とかスペイン語とか朝鮮語とか日本手話とかアメリカ手話とかだけではなく、その人個人の癖もあり、愛という言葉を大事にする宗教者や、意味はないということを意味の力を使って力説する人や、流行語に敏感でよく使いたがる人など、人それぞれだ。どの言葉を使うことになるかは、必ずしも個人の意思だけで決められないけれど、仮装の一種であることだけは確か。つまり、着替えることはできる。でも言語を完全に脱いで生きることだけはできない。
言語から離れられず、でも仮装として一喜一憂する姿を、言語で表すのが、たぶん詩なのだと思う。私は詩が何であるかをよくわからないということが長年の悩みなのだけど、今はそう考えている。
その意味で、西崎さんの書く文は、おしなべて詩だと感じる。先に引用したメールの文も、ツイッターの投稿も、西崎さんから発せられると詩になってしまう。これはもう意思の問題ではない。息を吐けば、詩。
きっと、tanbunとは、そういう言葉を指すのではないか。
この3冊の本の合間、ページの合間には、ときどき文がこぼれ落ちている。例えば、『特別ではない一日』を開くと、冒頭に、
「けれどぼくたちは住むところ以外はだいたい失っていた。」
と書いてある。このような文が、ページのあちこちに散りばめられている。

最初は、西崎さんが詩のような断片を書いてはさんでいるのかと思ったが、本を読んでいくと、収められたtanbunの中の一文が、本文から迷いはぐれてぽつねんとたたずんでいるのだった。それが詩に変身するのである。
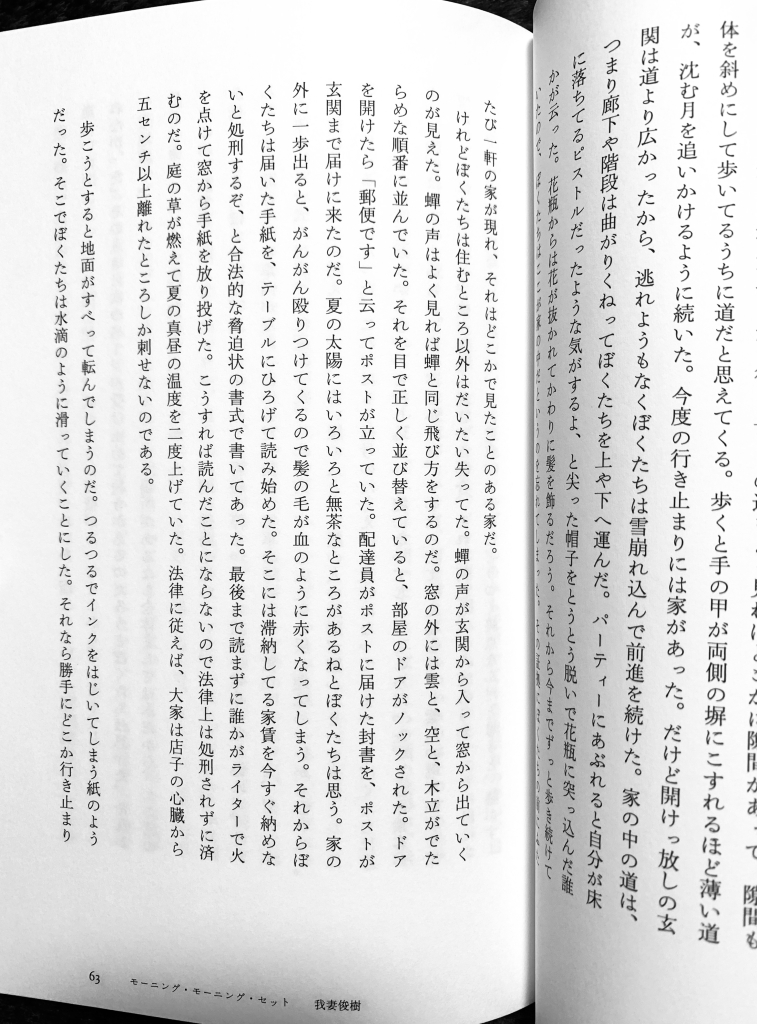
そう、文章自体が解体されてもかまわないのである。文脈の中で互いに支え合いながら存在しているはずの文を、一つだけ取り出して置いてみると、独立した文になって何か別の感触を帯びてくる。tanbunは、文脈を読み取ることに失敗してもいいのだ。好きな文や言葉だけつまみ読みしたっていいのだ。
3冊に収められているtanbunは、その大半が小説に見える。フィクションに感じられる。それは、エッセイとか小説とか詩といったジャンル区分を意識しなくてよい、となったとたん、エッセイを支えている「文中に虚構は書かれていない」という前提が消えるから。どれほど書き手の体験を書いているように見えても、虚構やアレンジが入っているかもしれないとなると、それは小説と感じられてくるのだ。tanbunは、存在自体が根源的な小説論、文学論である。
ちなみに私は、『移動図書館の子供たち』に、「おぼえ屋ふねす続々々々々」という、ボルヘスの短編「記憶の人、フネス」をもとにした二次創作を書いた。書き終わったら、「西崎さんの仕掛けた罠にはまった」と悟った。テーマに「図書館」と提示されたとたん自動的にボルヘスへと駆け出してしまう、私の傾向。そして、期待の地平を考えずに自分のためだけに書くことの、とてつもない難しさ。自由と解放というのは、じつは最も書き手を縛る不自由なのである。

この巻には、書いた人たちの一行詩が記された栞「貸出カード」が付属している。どの書き手のものに当たるかは、買ってみてのお楽しみ。


このエッセイを考えているころ、本屋で西崎さんの新刊を見つけた。
『本の幽霊』。

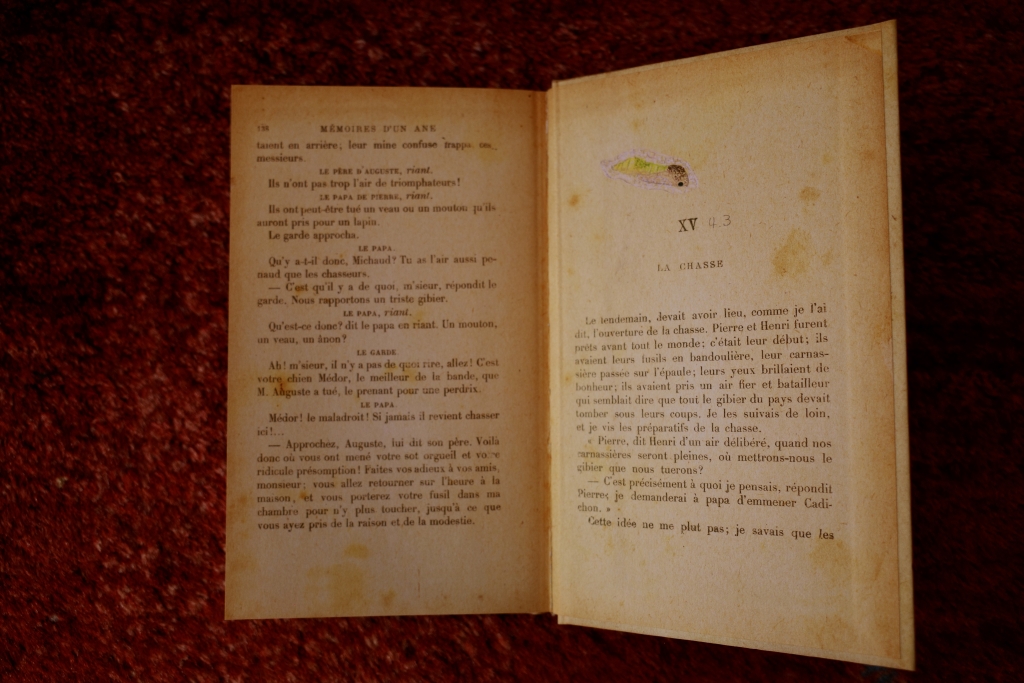

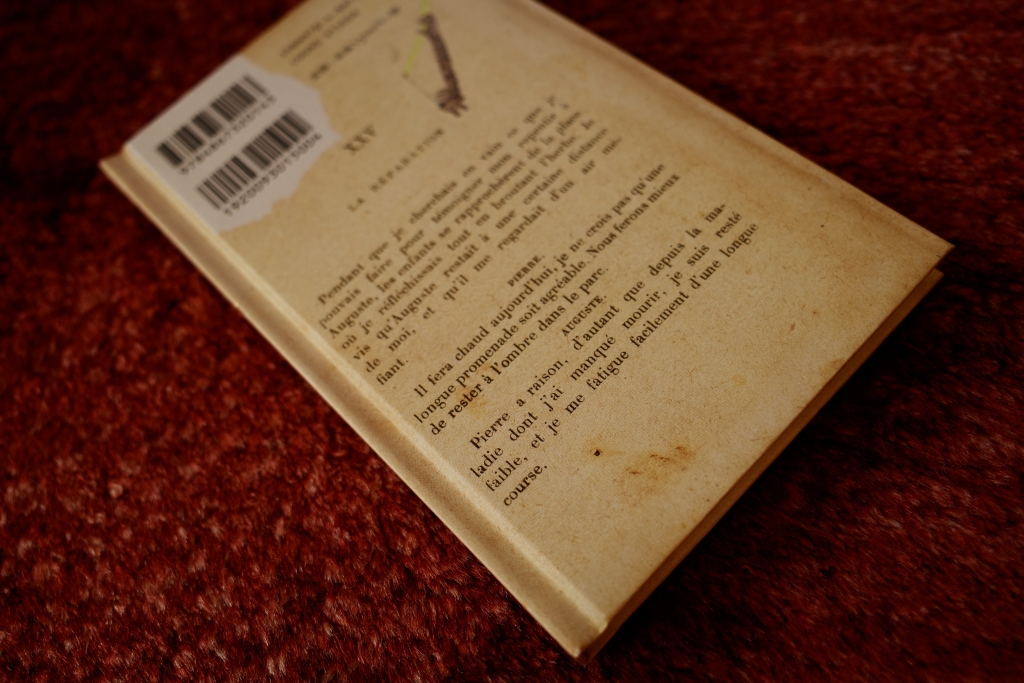
この装丁、このタイトル、この小説の底知れなさ。私は摂取するなり、死なない致命傷を負ってしまった。
1965年アメリカ・ロサンゼルス生まれ。1997年『最後の吐息』で文藝賞、2000年『目覚めよと人魚は歌う』で三島由紀夫賞、2003年『ファンタジスタ』で野間文芸新人賞、2011年『俺俺』で大江健三郎賞、2015年『夜は終わらない』で読売文学賞、2018年『焔』で谷崎潤一郎賞を受賞。新聞連載していた『ひとでなし』を、2023年夏に刊行予定。