黒川晝車
1997年生まれ。愛知県生まれ千葉県育ち。筑波大学比較文化学類卒。専攻は日本民俗学。Youtube/Podcast番組「ゆる民俗学ラジオ」「ゆる音楽学ラジオ」でパーソナリティをしながら、㈱pedanticの経営する「ゆる学徒カフェ」にて雇われ店長として勤務中。大きな草原が大好きなのでモンゴル及び中央アジアにも関心が強く、隙を見ては渡航を企てている。

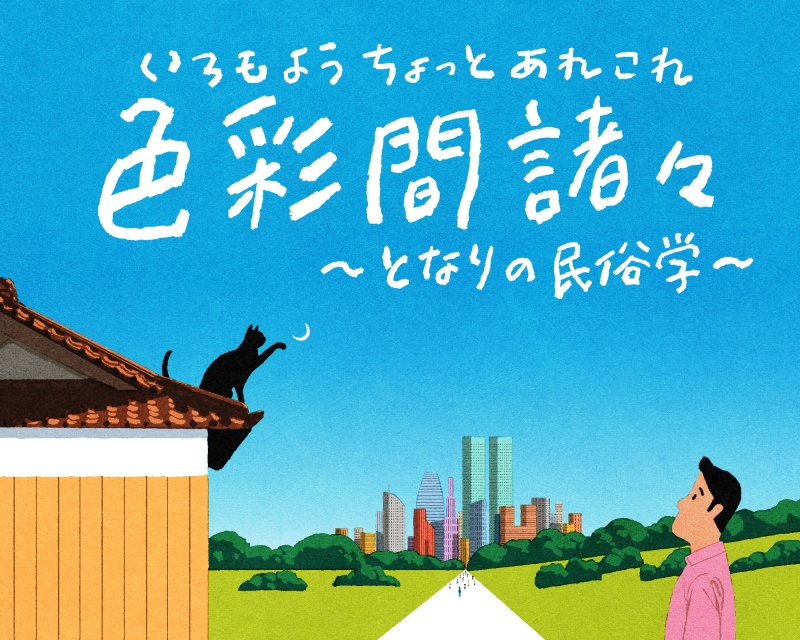 Illustration 飯田研人
Illustration 飯田研人
今回のテーマ:『箒』
民間信仰の上で箒神は、確かに存在するのだ。
こんな時お役立ちなのが俗信だ。日本人が箒という道具にどんなイメージを持っていて、掃除道具として使用する以外にどのように利用していたのかを調べれば、箒神が何者なのかは見えてくる。
するとまず気付くことができる意外な事実がある。それは、箒と出産との深い関わりだ。箒は出産の現場、それも陣痛が始まっていよいよ赤ん坊が産まれてくるというタイミングになって登場することが多い。とりわけ「出産のとき、箒を逆さに立てると安産する」という俗信は全国的に採集されている。箒の置き方と言えばふつう、あのケバケバした部分を下にして立てかけておくのが一般的な保管方法だが、わざわざそれを逆にするのだ。このようにした箒にご飯を供えたり唱え事をして、より確実な介助を願う方法もある。またこれを行うのに建物の内側であるか外側であるかは必ずしも問わないようで、地域によっては産室(出産のために特別に設けられた部屋・空間)の中、妊婦の枕元で行ったという話もある。また、高知県吾川郡の山間部ではこんなことが伝えられていた。
「ホーキガミが立ち寄ってくれないと産ませてくれないといって、産気づくと箒を神棚に供えて安産を祈る」
はっきりと箒神の名前が登場しているのが確認できる。
そう、箒神は一般に「出産に立ち会う神」として語られるのだ。ここでは出産の決定権さえも箒神が握っているとされており、普段は近くにいないが出産の現場には欠かせない、迎え入れるべき神霊として周知されていたことがうかがえる。一年の決まったタイミングや特定のライフイベントの折、遠方からやってきて恵みを授けてくれる神霊のことを民俗学では「来訪神」と言ったりする。箒神は箒をよりどころ(依り代)とする来訪神と言っても良さそうだ。こうして神が宿り得るとされているのもあり、箒には「またいではいけない」とか「踏んではいけない」という禁忌も伝わっている。
ちなみにさっき紹介した年末の「煤払い」という大掃除は家の保守管理や衛生状態の確保という目的がある一方で、歳神という神さまを招き入れるための空間浄化の意味合いもあった。煤払いをした後、煤竹は小正月に行われる左義長などと呼ばれる、盛大なお焚き上げで燃やすことになっていた。このことからもこの大掃除には清掃以上の役割があったことがうかがえる。そして歳神は来る年に幸福をもたらす外からやって来る神であり、来訪神の一種である。
ただ立てかけるだけではなく、出産にあたってより積極的に箒を呪具(呪術的な論理に基づき、目に見えない何らかの効果を期待して運用される物)として利用したらしい話も採集されている。なんでも、難産の予兆や陣痛の到来があると、出産に立ち会った女性の親族や産婆(助産師)などが、妊婦の腹部を箒で掃いてやることがあったらしい。いかにも優し気な動作であり、実際にリラックス効果があったんじゃないかと思う。また少々趣きが異なるが、箒で人を叩くと叩かれた人間が「お産が重くて苦しむ」ことになったり、「双子を懐妊してしまう」とも信じられていた。これは箒で人を叩くことを戒める禁忌であり、双子の忌まれる時代があったことも示唆される興味深い伝承だ。このように見てみると、箒と出産とは浅からぬつながりがあることがわかる。
出産という特別なライフイベントの場ではなく、日常のあんな場面やこんな場面でも箒は登場する。例えば「長居しているお客さんにはやく帰って欲しいとき」。こんな時も箒を逆さに立てると良いそうだ。お産の神は招き入れ、迷惑な訪問者は追い出す、というツーウェイの効果があるらしい。また、耳の中に入った虫を早く追い出すのにも使えるそうで、この場合は箒を枕にするらしい。虫からしたら草木の繊維の束でできている箒は、藪に見えるのかもしれない。それなら自ずから出てくるのも納得がいく。箒の枕はまた、アルコール由来の酔いを醒ますのにも効果があるとされていたそうだ。癖の悪い酔っ払いに痛い目を見させる言い訳として使えそうなので、みなさんも覚えておきましょう。
ところで興味深いことに、箒は全く異なるシーンでも掃除道具以外の役割を求められてきたという。それが「死の現場」である。妊婦にそうしていたように、死者(遺体)に対しても枕元に箒を立てることは行われていた。立てかけるだけではなく、遺体の上に置くこともあったそうだ。へえ、遺体に添える守り刀みたいだなあと思っていると、高知県の一部地域には箒といっしょに包丁も立てておくという例もあるのだとか。箒といっしょに立てかけるアイテムのバリエーションは豊富で、全て挙げているときりがないので割愛する。実際にこれを行っている人々に対して「なぜ遺体のそばや上に箒を置くのか」と質問すると、答えは多くの場合「遺体に悪さをしにくるものを遠ざけるか叩いて追い払う」というものであるらしい。やはり守り刀に求められる効果と共通している。
出産と死――真逆な場面だ。もっとも出産は、今日にいたるまで決して安心はできない危険を伴う局面だ。けれど命が生まれてくることと、命が失われているということの、ふたつの正反対な事態からくる印象の違いを拭い去ることはできない。そんな中で箒は、どちらの場面でも同じような振舞いを求められている。一見すると不思議な偶然のように思える。けれど実はこれらに見える箒への期待の根っこは、箒を持ってきた目的をシンプルに解釈してしまえばそれほどかけ離れているわけではない。むしろ共通している。
出産の場面で最も切実に求められることはなんだろう。それはスムーズに胎児が母体からとり上げられ、母子ともに健康に出産を終えること以外にはない。そのためにはできるだけ早く、負担が少ない出産ができるのが良い。だからこそ、いつの世も安産は願われる。
人の死に際して、遺された人々は亡くなった人物を支障なく他界へと送ってあげたいと願う。そのための葬礼は滞りなく行われる必要がある。主を失った肉体や霊魂を虎視眈々と狙っている、外の邪な霊たちに決して付け入られてはいけないし、這入ってきたときにはそれを力でもって牽制し、追い払わなければならない。
お腹に抱えた子どもの出産、遺体に群がる悪霊の撃退。これらはいずれも「手前から外へと、ある対象を動かしたい」という目的がある。どちらの目的も達成できる優れた道具なんてあるのだろうか。
ある。箒だ。
箒以上にそれに適した物が存在するだろうか。少なくとも、生活の周囲には存在しなかったに違いない。箒は掃く道具であり最も得意な仕事は、箒を持った動作主から見て外側へと塵芥を掃き出すことだ。風が吹くたびに舞いあがって玄関前や庭を散らかす塵芥や落ち葉は、一粒一枚ずつ対処していてはいくら時間がかかっても足りない。家の中だってそうだ。人間は生きているだけで驚くほどの塵埃を出すもので、これも指や手でどうにかできるものではない。そういった煩わしさを箒はいともたやすく解決してくれる。この頼もしさを僕たちは忘れがちだけれど、小学校の掃除の時間に丁字箒をはじめて借りて使った時のように、そこには快感とかある種の感動があったりする。
「なんて便利なんだろう」――人は生活の中で箒という道具の、目の前のものを外側へと容易に移動させることができるそんな利便性に惚れ込んだ。そしてそのまま信仰世界に持ち込んで「箒神」を生み出したのだ。
こういったことを踏まえてみると、最初に紹介した水木先生の描く箒神に「逃げ惑う男」がいたのも頷ける。箒神がしっかりと「外部へと掃き出す」という仕事を全うしているのを表現しているのだ。彼はきっと、掃き出され追い払われるべき存在だったのだろう。いっしょに描かれていた箒やチリトリを盗みにでも来ていたんじゃないだろうか。彼は招かれざる客だったのである。
一方で、この水木先生の元ネタになった鳥山石燕の絵の方はと言うと、男性は描かれていない。絵としてはただ垣根と箒、チリトリ、落ち葉、箒神があるだけである。ただ文章で言えばこちらにも余白部分に解説文が記されていて、図鑑としての体裁は整っている。
最後に、こちらの解説文をご紹介して、石燕がどのような解釈で箒神を描いたのかを確認しておこう。
原文はこうである。
【原文】
野わけはしたなく吹けるあした、
林かんに酒をあたゝむるとて、
朝きよめの仕丁のはきあつめぬるはゝきにやと、
夢心におもひぬ。
以下、黒川訳。
【黒川訳】
秋の野を駆け抜ける強い風が激しく吹いたその翌朝、
白居易の言うように秋の風情を楽しもうと、
門前を掃いて清めた使用人が紅葉を掃き集めるのに使った箒であろうかと、
そんな風に私は解釈している。
誰が雅なことを言えと言いましたか。寝言は寝て言って欲しい。
(第3回 おわり)
1997年生まれ。愛知県生まれ千葉県育ち。筑波大学比較文化学類卒。専攻は日本民俗学。Youtube/Podcast番組「ゆる民俗学ラジオ」「ゆる音楽学ラジオ」でパーソナリティをしながら、㈱pedanticの経営する「ゆる学徒カフェ」にて雇われ店長として勤務中。大きな草原が大好きなのでモンゴル及び中央アジアにも関心が強く、隙を見ては渡航を企てている。