dao-dao(ソヨゴ編集部)
日本印刷社員。soyogoとhon amiという2つの新ブランドを立ち上げて、事業を軌道に乗せるべく日々試行錯誤を続けながら、土日は子守りに奮闘中。

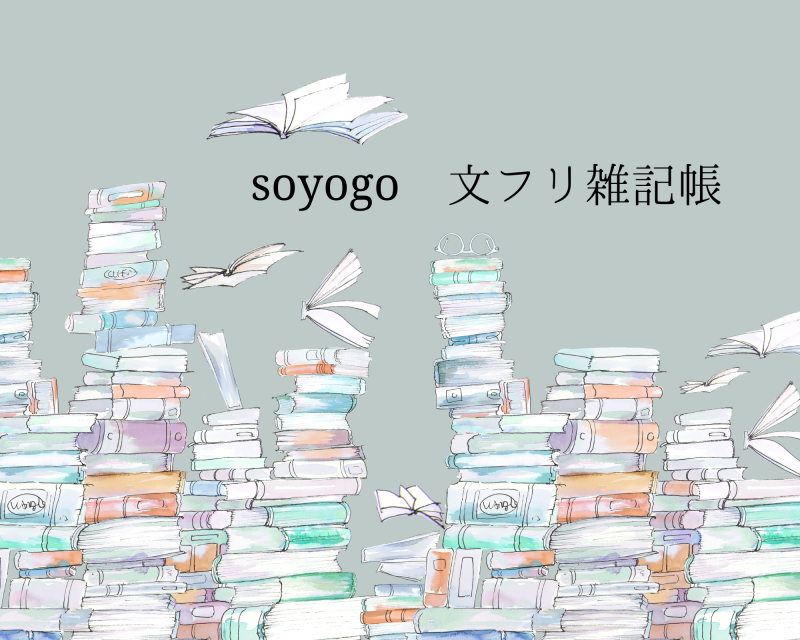
「売り子があんたじゃなかったら、もっと売れたんじゃないの?」
文学フリマ東京38の翌日、会社で仕事をしていると同僚が隣にどかっと腰を下ろして私に声をかけてきました。一番気にしていることをさらっと言われ、筆者は苦笑いするしかありません。
この男は、文フリに初出店している私と後輩(ともに男)の様子を夫婦で会場まで見に来てくれたのですが、とにかくわれわれの見た目が良くなかったそうです。
「やる気が感じられないのよ、やる気が。笑顔もないし、誰も寄り付かないでしょ」
やる気が感じられないという感想は心外ですが、「誰も寄り付かない」という彼の指摘は的を射ている可能性も十分にあり、反論できないというのも事実。
40歳過ぎるまでレジに立った経験のないおじさんがはじめての接客に挑んだわけですから、どんな立ち振る舞いだったのかは想像するだけでおそろしい。お釣りを出す作業ですらあたふたしてしまう場面も何度かありました。
一方で、文フリ常連客である女性社員は、
「初めてでそれだけ売れたら、すごいと思いますよ」
とはげましてくれます。
今回の結果をどう受け止めればいいのかよく分かっていませんが、文フリという舞台に初めて立ってみて、本を売ることの難しさを身をもって体験することができたのは事実です。
自分で文章を書き自分で本を作る人たちがこんなにたくさんいて、数えきれないほどのさまざまな本が販売され、買い求める人たちで会場がごった返している、という事実を目の当たりにしたことは、筆者にとってかなり衝撃の体験でもありました。
この連載は、印刷会社勤務の筆者が文フリに初出店を遂げるまでの記録です。
筆者の場合、企業の事業の一環として取り組んだわけですから、多くの方にとってあまり参考にならないかもしれませんが、これから文フリに出店してみようかな、と思われている方にとって、もし何かお役に立つことがあれば、という思いもあり、ここに書き記すことにいたします。
2024年はウェブメディアsoyogoからいよいよ紙の書籍を販売する年になる、ということで、前年の年の瀬あたりからsoyogo booksというレーベルを立ちあげて準備を進めていました。
そんななか、とある先輩から
「来年5月に文フリあるでしょ。あれに出てみなよ」
とのアドバイスが。
「5月って、たぶんまだ本ができていないですけど」
「いいじゃん。何かつくれるでしょ。顔見せ、しといたほうが良いよ」
とのことで、2023年の12月に出店申請をしたのです。ただ、抽選結果が3月に分かるとのことで、結局その日までとくに何も準備をしないまま時間が経過したのでした。
文学フリマ。存在はもちろん知っていますが、これまで参加したことはありませんでした。そんなイベントにいきなり出店側として関わることになるとは、ちょっと緊張します。出店計画を立てるにあたりいろいろと調べていると、サイトにはこんなテキストが掲げられていました。
文学フリマとは、文学作品の展示即売会です。
出店者が「自分が〈文学〉と信じるもの」を自らの手で販売します。
文学とは何ぞやという非常に難しい問いに対して、おのれがそう信じるもの、という考え方が提示されており、ハードルが上がっているのか下がっているのか判断がつきかねますが、可能性がぐんと広がる感じはします。
夏目漱石やシェイクスピアだけが文学じゃないよね、ということだとは思うのですが、筆者が急きょ小説を書いて文学だとのたまい販売するわけにもいかず、いろいろと頭を悩ませておりました。
さて、soyogo booksの第1弾として発売する予定の作品は「猫にご用心~知られざる猫文学の世界」です。翻訳家・大久保ゆうさんのセレクトによる、とある猫のキャラクターを主題とする文学作品の翻訳アンソロジーであり、非常に読み応えのある本になると思います。
となると、soyogo booksが文フリに出品するzine的な書籍の最初の著者として、文学からサブカルまで幅広い知識を持つ大久保さんにご協力いただくのは話の流れとしても自然だと思い、相談することにしたのです。それに、知られざる海外作品を紹介するという企画は、ちょっとワクワクしてきます。大久保さんにはすぐにご快諾いただき、いくつか素材も挙げていただきました。あれもこれも、と目移りしてしまいますが、時間もないため2冊に絞ることに決定。
1冊は19世紀のイギリスでつくられた絵本、もう1冊は1940年代にアメリカで書かれたある短編小説です。
文学に限らずどんなアートにも必ず歴史があり、先人たちの仕事が参照されながら新たな作品が生み出されていることを考えると、過去に焦点を当てることには大きな意味がありそうです。
それも、歴史に埋もれてしまった、あるいは読む機会がなくなってしまった海外の書籍を日本でよみがえらせることは文化的に意義のあることだと考えたのです。文学を文化のひとつと考えると、今の筆者にとって「自分が〈文学〉と信じるもの」、それは歴史に埋もれてしまった海外の書籍であり、その書籍を翻訳して現代によみがえらせるという営為である、と結論づけました。
・・・と、理詰めで考えるとなんとも面白くありませんが、大久保さんが挙げてくれたラインナップを見て、単純に面白い本が作れる気がしたのです。なくても別に困らないけど、あると日常に彩りを与えてくれる、そんな本を作ってみたいと思いました。
次回につづきます!
(第1回 おわり)
日本印刷社員。soyogoとhon amiという2つの新ブランドを立ち上げて、事業を軌道に乗せるべく日々試行錯誤を続けながら、土日は子守りに奮闘中。